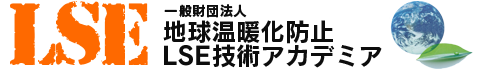LSEアカデミアニュース40号 電磁波と健康:その係わり(1) ~ ヒトは電磁波に慣れている? ~
1.プロローグ 「ESP 事業」のミッションは、 【ESP 事業】=【省エネ】+【新価値提供】。 省エネで経費と CO2を削減することは当然ですが、 これに「新しい価値を提供」して初めて「ESP 事業」 となるのです。「新しい価値」とは「ESP 事業で職場 がより明るく快適、健康的になった」「設備機器の誤 動作が無くなり、寿命も長くなった」「親しみの湧く 店舗になった」など「より安全・健康」への価値です。 振動・騒音・照明・温度・湿度・気流・異臭・・・これら体 感できる阻害因子よりも厄介なのが目に見えない「電 磁波」です。電磁波は身近な家電製品をはじめ医療機 器、乗り物、高圧線、電波基地局、等々から放出され、 私たちは電磁波飛び交う環境下で暮らしていますが、 平素は気にすることはありませんでした。 しかし、「ペースメーカーが携帯電話からの電磁波 で乱れ、命が危険にさらされた」一件以来、「電磁波 と健康との係わり論争」が熱気を帯びています。未だ 確かな科学的証明はなされていませんが、電磁波が人 体に何らかの影響を与えていることは事実なのです。 「ESP 事業」で導入する省エネ機器システムの選 定には「電磁波回避」が必須です。「予防原則」こそ 「より安全・健康」への価値提供なのです。本「電磁 波と健康:その係わり」シリーズの目的は「電磁波を 知って防ぐ」ことを会得いただくことです。 続きは会員ページより