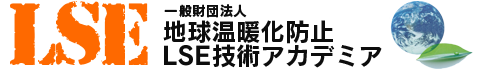再生エネルギーの「エコ・エネ」評価(9) ~ 燃料電池は水素社会を支えられるか ~
1.燃料電池の果たす役割 前36号で「我が国が『パリ協定』の約束を果たすには水素社会へ2030年に本格移行しなければならない」こと、そして「必要な『水素』はどうやら確保できそう」なこと、を概説しました。 次の課題は「燃料電池(FC: Fuel Cell)」の低コスト化と長寿命化です。FCは水素社会の一般家庭やオフィスのコジェネ(電気+熱:エネファーム)、燃料自動車(FCEV)のエンジンや非常電源など、きわめて重要な生活基盤を支える役割を担うのです。2025年には実用レベルに達しなければなりません。技術開発の苦悩など「燃料電池は水素社会の基盤技術になりうるか」を本号で考えます。 続きは会員ページにて